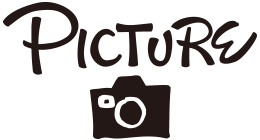あつーーーい!!
あっという間に8月ですが、皆様夏休み満喫してますか???
来月には9月!!
七五三シーズンの到来!
PICTUREも9月から始まる新しいサービスに向けて、準備していまーす!
準備が整い次第すぐにリリースしますのでおまちくださいね!
七五三の準備はいつからが正解?流れをチェックしてみましょう!

七五三の準備は早ければ早い方がいいと言われています。いつ頃どのような準備をすればいいのか、1年の流れをシーズンに分けてご紹介いたします。
春:予定を立てよう!

七五三シーズンは、春の気配が感じられる3月ごろから始まります。
ご祈祷や記念撮影、食事会の予約、衣装の用意などさまざまな準備がありますので、時間に余裕のあるこの時期から進めておくと安心です。
3~5月は衣装の新作が発表され、写真館では前撮りの受付が始まります。
人気の衣装をチェックしたり、前撮りキャンペーンを比較したり、この時期ならではのメリットを考慮に入れて予定を立てましょう。
夏:早めの前撮りがおすすめ

夏は、夏休みを利用した前撮りがおすすめの時期です。
家族写真を撮影する場合も、家族全員のスケジュールが調整しやすく、お得な平日撮影も検討に入れられます。
また、着物で撮影する場合は、当日のリハーサルにもなりますよ。
夏休み前後までは、まだ衣装レンタルや前撮りの予約も取りやすいので、お気に入りの衣装で落ち着いて撮影したいなら、ぜひこの時期に済ませておきましょう。
秋:神社にお出かけシーズン

秋は、いよいよ七五三本番、お出かけシーズンの始まりです。
11月15日を中心に、10~12月の間に参拝されるご家庭が多いようです。
シーズン中は週末の吉日は混みやすく、小さいお子さまには負担が大きい場合もあります。
神社までの移動を工夫したり、移動時は動きやすい服・靴に変えたり、お子さまが疲れないように準備してあげましょう。
また、9~10月頃は気候も安定し、紅葉が美しい季節です。
七五三を目前に写真館での記念撮影も増えてくるので、希望日に空きがないといった状況に遭遇することも少なくありません。
秋に前撮りをご希望であれば、遅くとも2~3カ月前までには予約を取っておくことをおすすめします。
冬:まだ間に合う後撮り

七五三本番が去った12~2月は、後撮りのシーズンです。この時期の撮影は、予約も取りやすく落ち着いてゆっくり撮影できるところが魅力。3歳のお子さまの場合なら、イヤイヤ期が落ち着く頃なので、比較的スムーズに撮影が進むでしょう。
前撮り同様、当日とは違った衣装で撮影ができ、雰囲気のある演出にすればそのままクリスマスカードや年賀状にも利用できます。
後撮りキャンペーンや特典付き撮影プランなどを実施する写真館も多いので、上手に利用すればお得に記念写真が残せますよ。
よく問い合わせで多い質問にもお答えしますね!
七五三のお参りを行う時期はいつ?
七五三のお参りは11月15日が中心ですが、ご家族の予定や混雑状況を考慮して行うことも一般的です。
七五三は暦の上では11月15日に行うのが慣習とされていますが、実際には9月から年明けまでの間に計画するご家庭も増えています。
特に秋の行楽シーズンは神社が混雑しやすく、写真撮影の予約が集中してしまうことも珍しくありません。
ご家族やお子様の予定に合わせて、落ち着いて参拝できる時期を選ぶのがポイントです。
平日を選択すれば大安でも比較的空いている場合があり、ゆったりとした七五三を楽しむことができます。
七五三シーズンの秋以外の時期や、一年を通してお参りが可能な神社やお寺もあるので、事前に問い合わせて確認をしておきましょう。
地域によっては、氏神様の境内が特に盛り上がる日取りを重視する習慣が残っていることもあります。
逆に、混雑を避けたい場合は早めや遅めの時期に改めて日を設けるのもおすすめです。
大切なのは神様への感謝とお子様の笑顔が最優先になるという考え方であり、ご家庭の都合と家族の体調を第一に柔軟に日程を組みましょう。
七五三の参拝時期に関する注意点
七五三参拝は日取りや混雑、体調管理など、事前に気をつけておきたい点がいくつかあります。
七五三はハレの日として華やかに行われる一方、人気の神社や写真スタジオでは予約や混雑が気になるところです。
想定外の混雑により、お子様の負担が増すとせっかくの節目が台無しになってしまうかもしれません。
さらに、秋から冬にかけての時期は気温がぐっと下がる日が多いため、防寒や体調管理の面でも準備が必要です。
限られた時間の中で順番待ちが長引く可能性もあるので、事前のプランニングをしっかり行いましょう。
●「大安」は混みやすい
六曜を気にされる方にとっては大安が好まれるため、どうしても希望者が集中しがちです。
特に11月の土日祝日の大安は希望の時間帯がすぐに埋まってしまう可能性が高いため、早めの予約をおすすめします。
スムーズに参拝をするためにも、可能であれば平日を含め選択肢を広げて検討しておくとよいでしょう。
●10~12月は体調管理に注意
日中と朝夕との寒暖差が大きい季節でもあるため、お子様の洋装・和装いずれの場合でも体温調節のできる羽織物を用意すると安心です。
神社の外で待つ時間が長いと、子供は退屈してしまったり体力を消耗してしまうことがあります。
参拝前にしっかり栄養と休息をとることも大切なので、スケジュールはゆとりをもって組み込むように心がけましょう。
普段から温かい服で防寒対策をしたり無理をさせないようにしたりして、お子様をはじめ、家族の体調管理は慎重に行うようにしてくださいね。
七五三をお祝いする年齢
七五三は男の子が3歳と5歳、女の子は3歳と7歳でお祝いするのが一般的ですが、地域やご家庭によってさまざまな考え方があります。
近代では満年齢でお祝いするのが一般的になっている一方、数え年で行う伝統を持つ地域も残っています。
ご家族の中で祖父母など年上の方の意見を取り入れる場合は、地域性を尊重して数え年で行うことも多いようです。
ただ、お子様の成長や発育具合に合わせることが大切なので、満年齢か数え年かにあまりとらわれず、無理のない時期を選んであげてください。
男の子でも7歳のお祝いをされるケースが増えているなど、近年は柔軟に対応される傾向があります。
●本来の名称と意味
七五三は平安時代に行われた三つの儀式が起源とされ、その後江戸時代に武家社会で定着し、庶民へと広まりました。子供の髪を伸ばし始める「髪置」、男の子が初めて袴を着ける「袴着」、女の子が初めて帯を締める「帯解」は、いずれも子供の健やかな成長を祈願する大切な儀式でした。
現代ではあらたまった形式こそ簡略化されていますが、子供にとっての成長の節目を祝うという意味は変わりません。
- ・3歳男女:髪置(かみおき)
- 古来は子供が生まれて髪を剃り、坊主にする風習がありました。
- 髪置は、幼い子供の髪を伸ばし始める儀式とされ、名前の通り、子供が大人の髪型に近づくきっかけともいわれています。
- 昔は病院や医療技術が十分ではなかった時代、子供の成長そのものが奇跡であり、大切に扱われました。

- ・5歳男子:袴着(はかまぎ)
- 袴着は、男の子が初めて袴を着用する通過儀礼です。武家社会が発達した時代には、身分の高い家庭ほど厳かに行われたとされています。
- 現在は袴の着用シーンも限られますが、歴史的には社会の一員として認められる区切りとして重要でした。

- ・7歳女子:帯解(おびとき)
- 女の子が本格的な和装となる帯を締めるのが帯解です。
- これまでは子供用の付け紐や簡単な帯を使っていたのが、正式な帯へと替えることで成長を実感します。
- 大人への第一歩として、華やかな着物姿に感動するご家族も多いでしょう。

●男女とも3歳・5歳・7歳のいずれもお祝いして良い
現代ではお子様の成長を祝う方法が多様化しており、男の子でも7歳でお祝いをするケースも増えています。
子供自身が「着物を着たい」「写真を撮りたい」と望む場合など、柔軟に対応してあげるとよいでしょう。
七五三本来の目的はお子様の成長を神様に感謝し、健やかな将来を祈ること。男の子も女の子も性別に関わらず3歳・5歳・7歳でお祝いしても問題はありません
。記念写真でも各年齢での表情やポーズの違いなど成長過程を楽しむことができるでしょう。
ご家庭で大切にしたい節目やお子様の意思を尊重し、家族の一体感を深める行事として活用してください。
●「数え年」と「満年齢」どちらがいいの?
現在一般的なのは満年齢ですが、伝統を重視する地域や家庭では数え年を選ぶことがあります。
あまりこだわらずに、お子様の体格や集中力、行事への理解度なども考慮すると良いでしょう。
ご家庭の考え方とお子様の負担を最優先に、ゆとりを持ったスケジュールを組んでみてください。
ご家庭の都合に合わせて、studio PICTUREで思い出に残る素敵な七五三のお祝いを

五三はお子様の成長を祝う大切な機会で、家族全員にとって思い出深い行事になるでしょう。
日取りや年齢の数え方など、厳しい決まりはありませんので、お子様の安心・安全を第一に考え、ご家庭に合ったスタイルで取り組んでみてください。
何より大切なのは、お子様とご家族が笑顔で過ごせることです。無理のないスケジュールと服装で、心に残る行事にしましょう。
studio PICTUREでは前撮り、当日撮影、後撮りと1年を通して七五三の記念撮影を承っております。
家族みんなで着物での撮影、リンクコーデも可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください^^ご予約はコチラから‼︎
撮影に関するご質問やご相談がありましたら
アディオス!!!